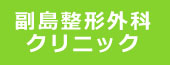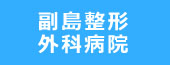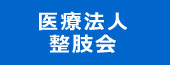安心の医療を支える麻酔
『手術中は麻酔で守られている』
麻酔科部長 前田 祥範

今回は、当院の麻酔科・前田医師に、手術にまつわる麻酔の役割や、術前検査の意味、そして術後の鎮痛管理について、わかりやすくお話を伺いました。
患者さんが少しでも安心して手術に臨めるように、前田医師の視点から“見えにくいけれどとても大切なこと”をお届けします。
Q) 「麻酔」と聞くと、どこか不安になったり、ちょっと怖い…。
手術そのものももちろん心配だけれど、「麻酔中は本当に大丈夫?」「術後の痛みは?」など、わからないことが多いです。
A) 手術や麻酔については、多くの皆さんが「怖い」「心配…」といった不安をもっておられると思います。
「麻酔」を一言でいうと、「手術を受ける患者さんを守っていくもの」と言えます。
手術では、皮膚を切ったり、血が出たり、同じ姿勢を長く続けたりといった、患者さんには負担となることを多く行います。
もちろん手術をする先生も、なるべく少ない負担で済むように努力をしていきますが、ある程度の負担はどうしても生じてしまいます。
このような患者さんへの負担を、可能な限り減らしていくものが「麻酔」という手段です。
手術中に痛みがないようにすることはもちろんのこと、長時間の手術でもストレスのないよう眠ってもらうことや、手術中の出血を補うために体液量を調整すること、血圧・心拍数や人工呼吸の管理、手術の後の痛みをとるための鎮痛法を行うこと、などなど多くのことを同時に行いながら安全に手術が終わるように努めています。
つまり、手術は怖いものかもしれませんが、実は麻酔は「患者さんを守っていくもの」なのです。

Q) 副島整形外科病院の麻酔科では、どのような体制で患者さんの安全と快適さを支えているのでしょうか。
A) 副島整形外科病院では、常勤の麻酔科医が2名、非常勤の麻酔科医が4名、勤務しています。
6名全員が麻酔科専門医という資格を持っており、経験豊富な先生ばかりです。
また、副島整形外科病院は、日本麻酔科学会が認定する「麻酔科認定病院」です。 佐賀県内では、佐賀大学医学部附属病院や県立病院好生館など12の病院が麻酔科認定病院として認定されています。(令和7年3月現在)
Q) 「麻酔科認定病院」について詳しく教えてください。
A) 麻酔科認定病院とは、常勤の麻酔科医が管理する全身麻酔症例が年間200例以上あることや、安全な麻酔を行うための施設・設備が整備されていること、専門医を育成するための十分な施設・設備が整備されていることなどの基準を満たしている病院として認定されるものです。
「麻酔科認定病院」についてはこちらでも説明していますのでご覧ください。
このように、副島整形外科病院では、施設などのハード面と、人材などのソフト面の両面から、みなさんに安全に手術を受けていただける体制を整えています。

Q) 手術中の麻酔について,また副島整形外科麻酔科の体制について詳しく教えていただき、安心できました。
ところで、手術前にはいろいろな検査がありますよね。
術前検査は、どのような目的で、どのような検査が行われているのでしょうか?
A) 手術を受けることで患者さんの体には負担がかかりますが、手術の種類によってかかる負担には違いがあります。また、患者さんの体の状態も患者さんごとにいろいろと違いがありますので、「この手術の負担がこの患者さんの状態と比べて大きくなりすぎないか」を手術前に正しく評価することが大切です。
このためわたしたち麻酔科医は、手術の前に次のような診察と術前検査を行い、問題ないかどうか評価しています。
これまでの病気の治療歴や、現在治療している病気の有無、飲んでいるお薬の種類などを確認し、これまでに気付かれていない病気がないかどうかもチェックします。
また、心電図や血液検査、尿検査、レントゲン画像、呼吸機能検査などを確認します。
最終的に、手術という負担がかかっても患者さんの状態が悪くなるような可能性は少ない、と判断できればOKです。
患者さんに当日の麻酔の方法をご説明して、術前検査は終了となります。
術前検査はある程度時間はかかるものですが、安全に手術を受けていただくためにとても大切な過程です。
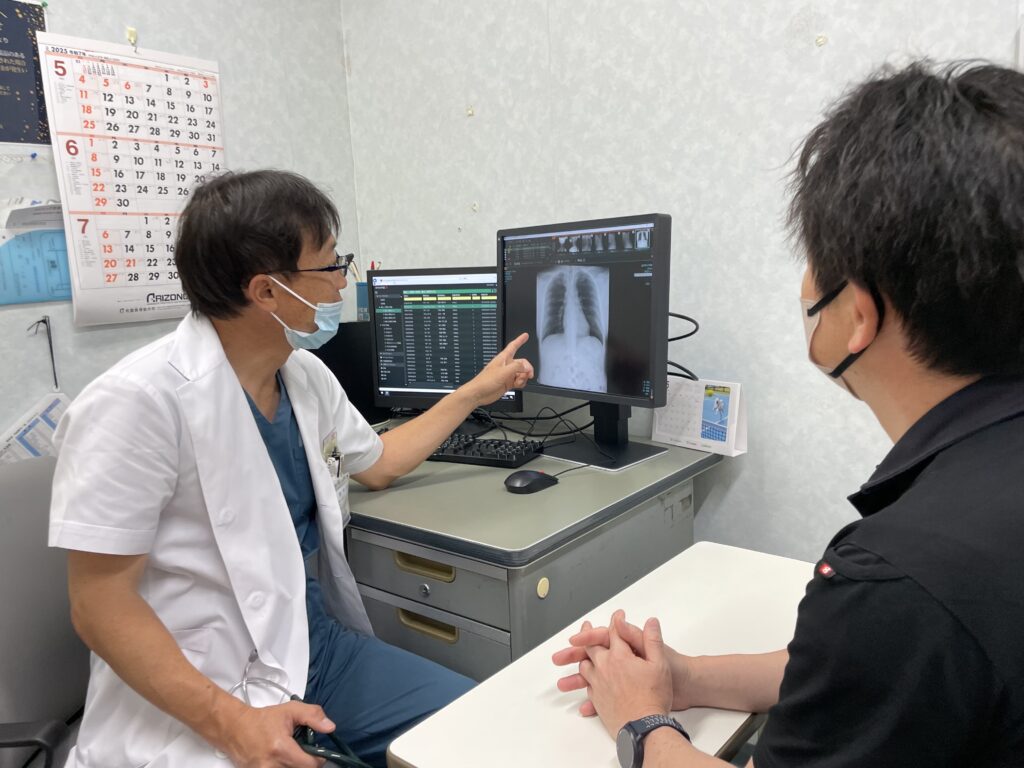
Q) 検査を通して患者さんの状態をしっかり確認した上で、麻酔の計画を立てていくんですね。
実際の手術では、どのような種類の麻酔があるのでしょうか?また、どのように使い分けているのですか?
A) 麻酔をどのような方法で行うかは、手術の種類や患者さんの状態によってひとりひとり異なってきます。手術を受ける患者さんにとって最もメリットのある方法を選んでいます。
① 全身麻酔
多くの手術でこの全身麻酔が行われます。全身麻酔の一番のメリットは手術中の意識がないことで、これにより患者さんは手術中のストレスから解放されます。
全身麻酔では、ほとんどの患者さんが一瞬で手術が終わったように感じられ、驚かれることが多いです。
点滴からお薬を注入したり、呼吸の酸素に混ざったお薬を吸ってもらったりして麻酔を行います。
全身麻酔中は、呼吸を補助するために喉に管を入れる場合もあります。管が入っても、眠っているため苦しかったりすることはありませんが、手術の後に喉の違和感を覚えられる方が一定数おられます。
② 脊髄くも膜下麻酔
難しい名前ですが、いわゆる「下半身麻酔」の一つで、腰の部分に注射をして麻酔を行います。主に足の手術の際に行い、全身麻酔と併用して行うことが多いです。
麻酔の効果が手術の後もしばらく続きますので、手術直後の一番痛みの強いときに麻酔が効いていて快適なことがメリットです。
麻酔が効いているあいだは排尿ができないことが多く、尿を出すための管を入れる必要があります。
③ 伝達麻酔(神経ブロック)
手術中の麻酔としても手術後の痛み止めとしても有効な方法で、これも全身麻酔と併用して行うことが多いです。痛み止めの薬を神経の通り道に注入することで、長時間の痛み止めとして作用します。
術後の痛み止めとして効果があるあいだは、効果部位にいつもと違う感覚が生じます。例えば、手の伝達麻酔を行った場合には、手がしびれたような違和感があったり手を動かしにくかったりしますが、麻酔の効果がなくなってくると元に戻ります。
上記のようないくつかの麻酔方法を組み合わせて、その患者さんに最も適した方法で麻酔を行っています。
「手術中は麻酔で守られている」という安心感をもって手術を受けていただけると、わたしたちも嬉しいです。

Q) 麻酔にもいろいろな種類があることがわかりました。
手術中は麻酔で痛みを感じないとのことですが、
術後の痛みについては、どのようにコントロールされているのでしょうか?
A) 手術のあとの痛みを減らしていくことも、麻酔の重要な役割です。
わたしたち麻酔科専門医は、神経ブロックや注射薬、座薬などの痛み止めを上手く調節しながら、なるべく患者さんに術後を平穏に過ごしていただけるように努めています。
しかし、痛みの管理は患者さん自身のご協力も不可欠です。たとえば、禁煙することも非常に大切な要素のひとつです。喫煙者では術後急性期の疼痛スコアが非喫煙者に比べて高く、鎮痛薬の必要量が多く慢性術後痛への移行リスクが高いことが知られています。
ご自身のためにも、ぜひ知っておいてほしいことのひとつです。

Q) 前田先生、今回は麻酔や術前検査、術後疼痛について詳しく説明していただきありがとうございました。
A) こちらこそありがとうございました。
分からないこと、不安なことなどございましたら術前に遠慮なされずにご相談ください。
Q) 手術中は麻酔で守られているという事が分かり、安心して手術をうける事ができると分かりました。
次回は当院で多くの手術をされている石井医師に膝の人工関節置換術について話を聞いてみたいと思います。
A) 石井医師は人工関節に限らず、鏡視下手術や骨切り術など数多くの手術をされています。石井医師、次回よろしくお願いします。